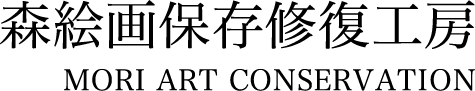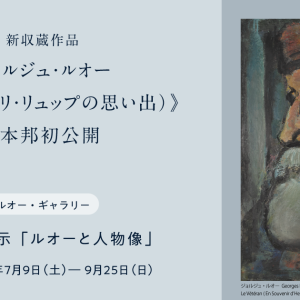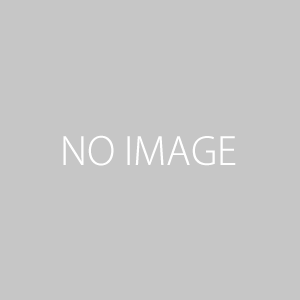Vol.2 ミレー「晩鐘」を見る
すべての名画は修復されている。
油彩画は一般に思われているほど堅牢なものではないし、小さな事故はつきものだ。たとえ管理に落ち度がなくても表面に塗布されているワニスは黄色く変色しやすく半世紀も経つと除去もしくは軽減しない限り絵の生命線ともいえる色彩がくすんでしまう。だから取引の対象となったり美術館に展示されたりしている19世紀までの名作はこうした処置も含めれば全て修復されている、と言っていい。

「晩鐘」拡大部分
絵は修復されているものだ、という認識でミレーの「晩鐘」を見てみる。すると、誰でも二人の人物の間に縦方向にくっきりと傷のように浮かび上がる線に目が留まるはずだ。そこが、まさに修復された部分である。
2003年開催された展覧会「ミレー3大名画」展にも出品されていたから注意深い鑑賞者のなかには気づいた方がいたに違いない。海外から作品を輸送して構成されるこのような展覧会では作品の状態調査書(コンディションレポート)を作成するなど出品作品の保存に関する仕事を修復家が担当することが多い。この時は私が担当し、間近で修復部分を点検して、あらためて好奇心をそそられて当時のフランスの新聞数紙を調べてみた。
悲劇は、1932年8月12日午後1時40分頃、ルーヴル美術館の展示室内で、ピエール・ギヤールという31歳の男によって惹き起こされた。職を失い、両親とともに住んでいた男は、特に普段と変わった様子も見せず優雅な着こなしでふらりと家を出た。そして、美術館に入り、「晩鐘」の前に立つといきなりポケットからナイフを取り出して切りつけたのだ。すぐにガードマンから取り押さえられたがすでに4箇所に傷がつけられた後だった。「俺は迫害されてきた。だが、これで俺は、認められるのだ!」数紙が男を半狂人と形容して、男の行動を理解不能と記している。

新聞に掲載されたピエール・ギヤールの肖像写真
「晩鐘」は、1889年の競売でアメリカ芸術家協会に落札されたが、当時すでに特別な存在であったこの作品の流出に反対する世論が高まり、その後フランス人に買い戻され、1909年にルーヴル美術館に寄贈されている。名画中の名画であるゆえの悲劇だったのである。
興味深いのは、その後の修復ついての美術館側の見解で、「始めるにあたって厳密な調査をし、手続きを踏んで進める」とあるあたりは既に一定の理念が確立されていることがわかるが、「切り裂かれただけでマチエールは全く失われていないので修復は比較的容易で2ヶ月ほどで終わるだろう」という見通しについては今では違和感を覚える。調査も議論も複雑化し、顕微鏡下で糸と糸をつなぎ合わせるような繊細な技術が想定される今日では期間を2年としても少ないかもしれない。「修復者は独自の技術をもっているが、彼らは嫉妬深く、秘密は明かされることはない」云々、という記者のコメントも時代が感じられておもしろい。
現在ではオルセー美術館で厳重に低反射ガラスに守られて展示されているが、修復家にとってその傷はなまなましく、いろんな問題を考えさせられる。